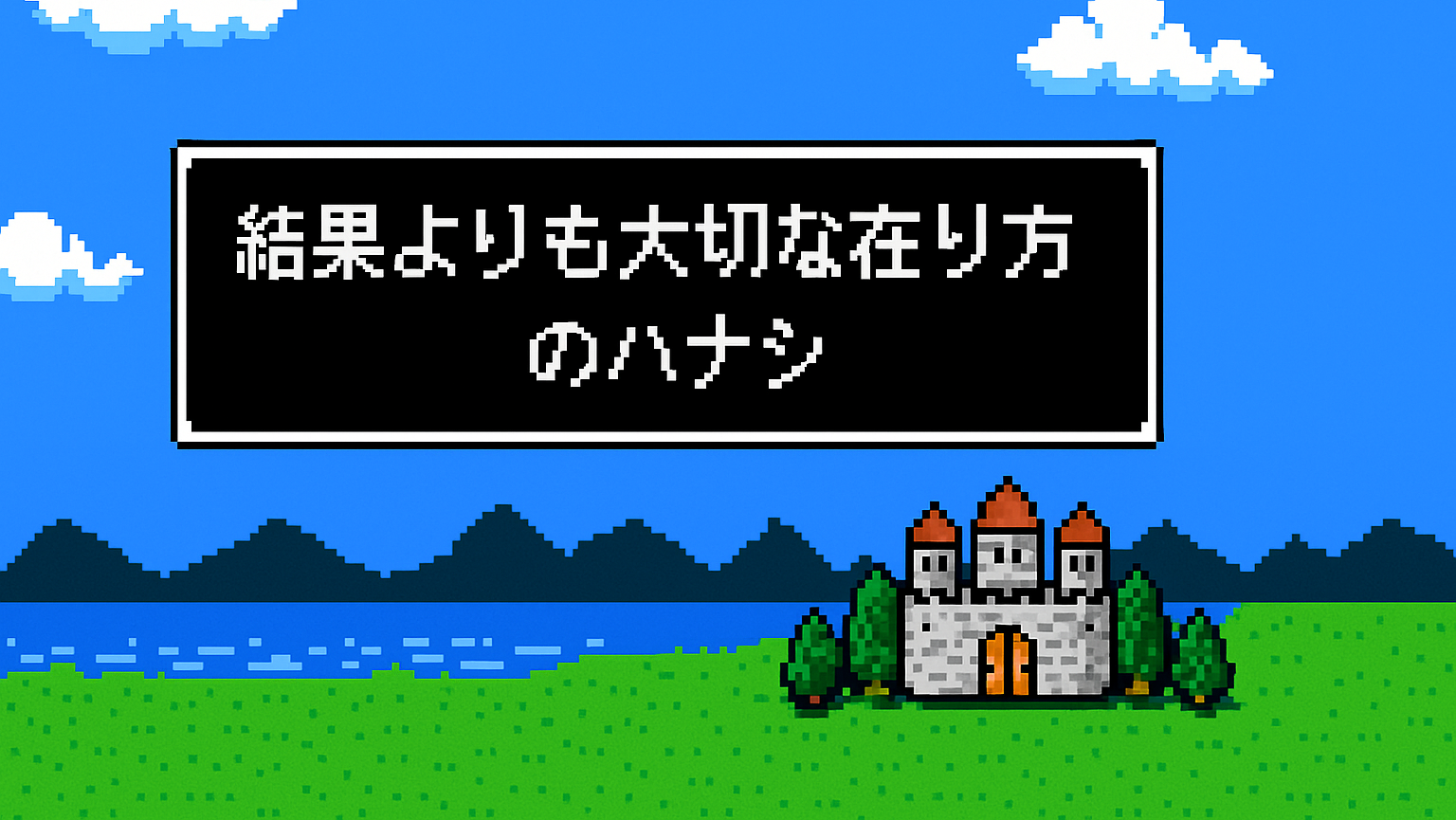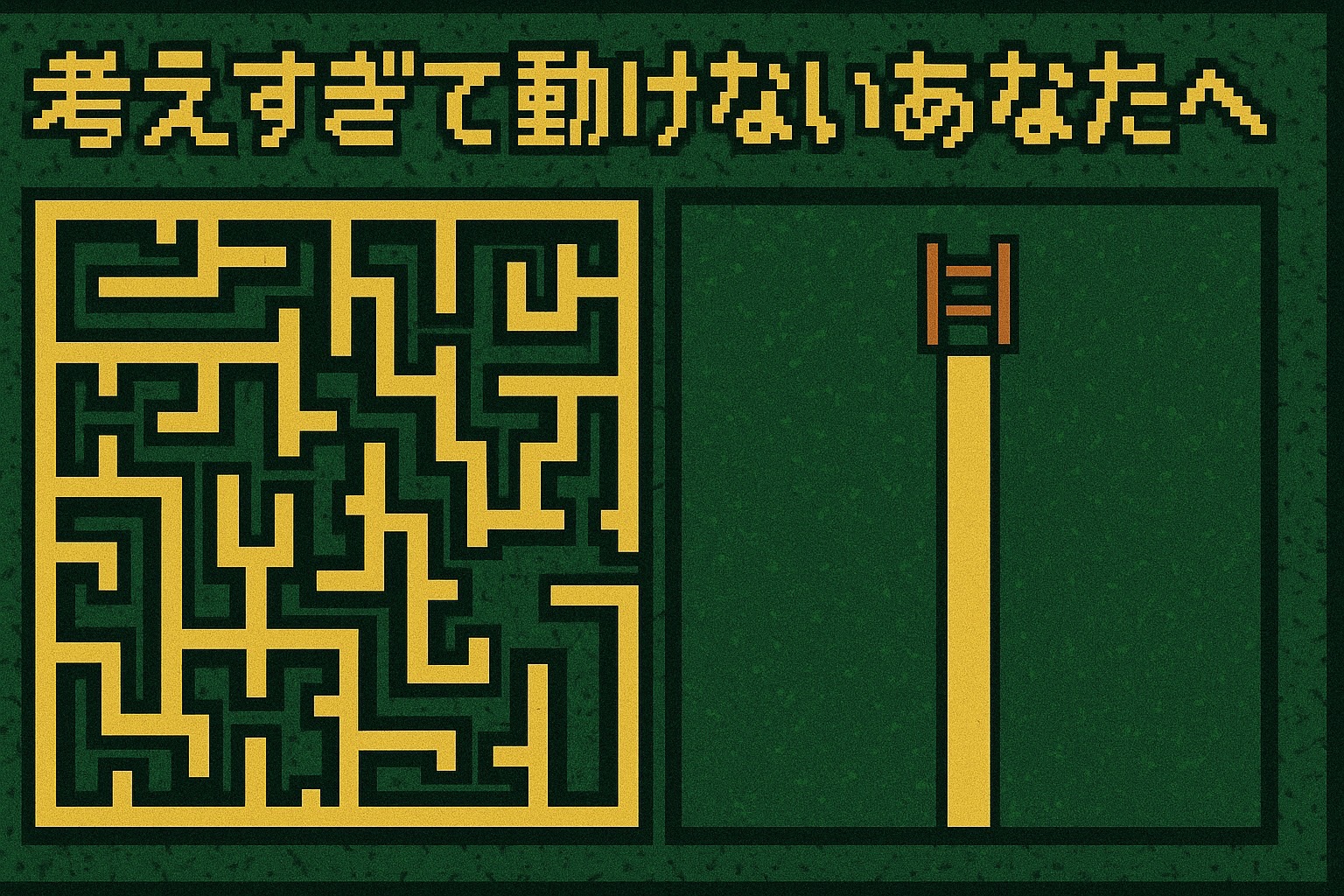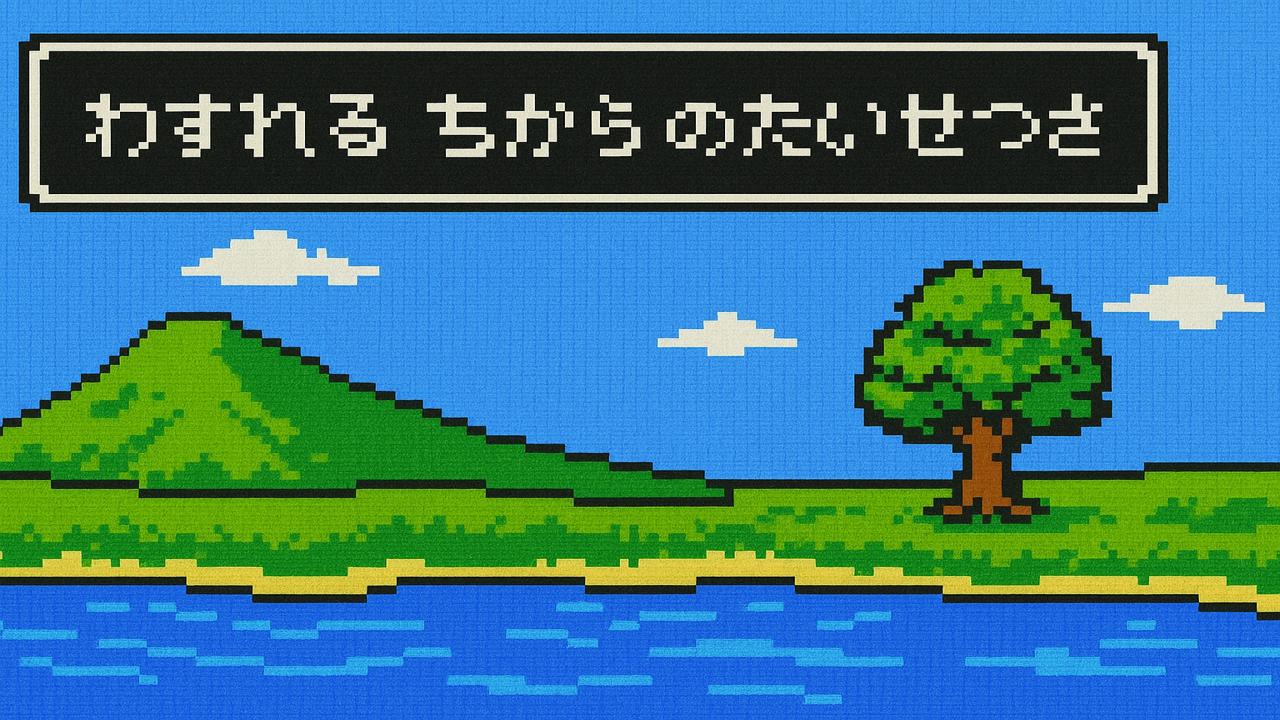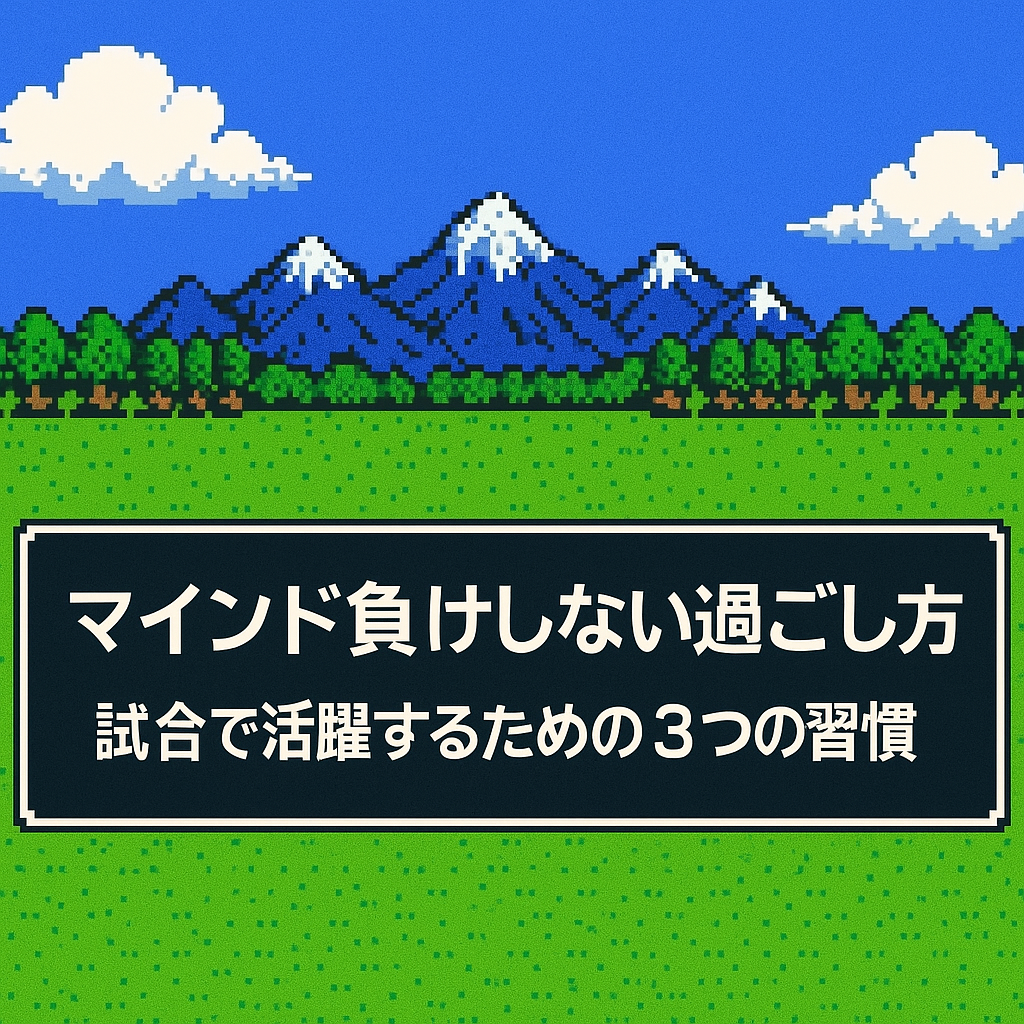【言語化しないから深くわかる】思考と感覚の使い分け
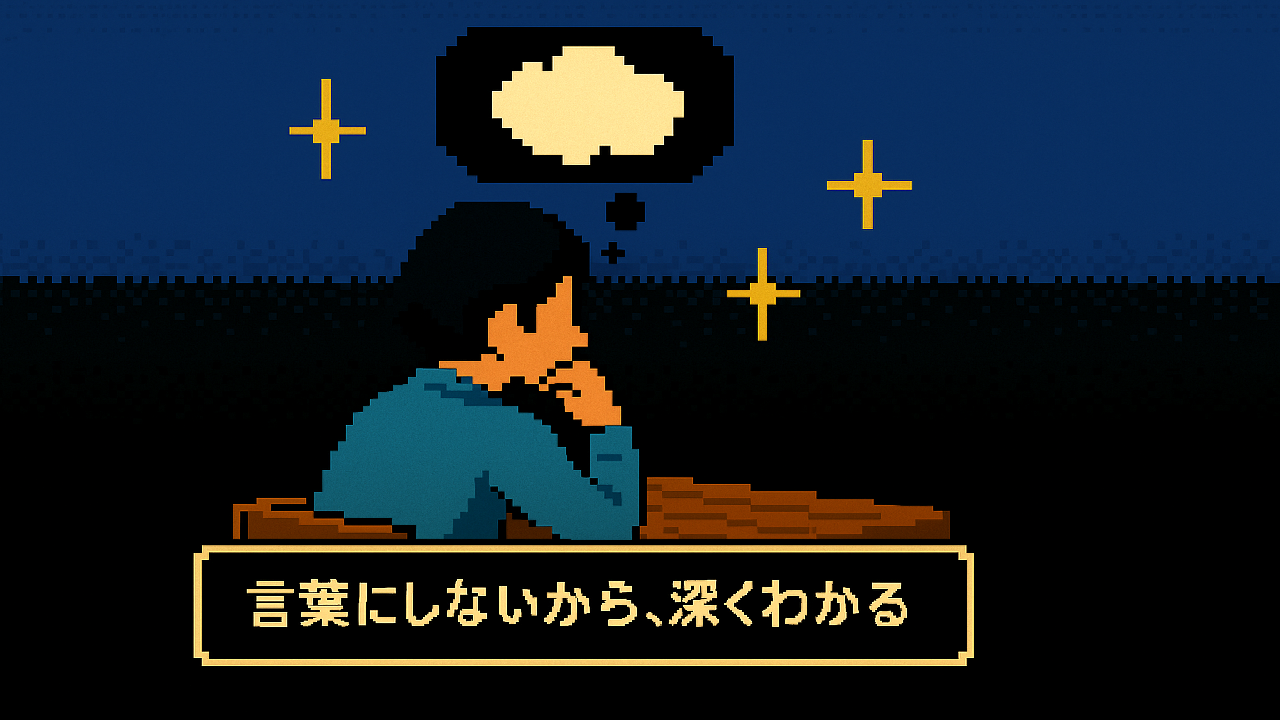
人からの説明が細かすぎて、頭が混乱したり、動きがぎこちなくなったりした経験はないでしょうか。私自身、バッティングでフォームを事細かに言語化して指示されたときに、「言われた通りにしなきゃ」と考えすぎて体がガチガチになってしまったことがあります。逆に、見よう見まねで動きを真似したり、「ここはフッと力を抜いて」などざっくり抽象的なアドバイスを受けたときの方が、不思議と動きのコツを掴めたという経験がありました。
「あえて言語化しない」ことには様々なメリットがあります。「考えるな、感じろ!」というブルース・リー名台詞も、ある意味この現象の本質を突いているのかもしれません。
この記事では、「言語化しない」ことがもたらす効果やメリットついて、私の実体験をもとに考えてみます。
言葉のせいで窮屈に
細かい言葉の指示に囚われすぎると、動きの自由が失われてしまうことがあります。例えば私の場合、バッティングフォームの矯正の時に、「◯◯の筋肉にチカラを入れて」「開きを抑えたいからこのタイミングでここを固定して」などと、細かく言語化された指導を受けたとき、頭で考えすぎてしまい、かえってスイングが不自然になりました。心理学では、物事を言語で細かく意識しすぎることで本来のパフォーマンスが阻害される現象が知られています。スポーツ科学の分野でも上級者ほど動作をひとつひとつ言語で意識するとパフォーマンスが落ちることが指摘されています 。言葉による分析に頼りすぎると、頭でっかちになって身体の動きにブレーキをかけてしまうのです。
言葉じゃないものから得られる理解
一方、言葉に頼らずに実際に見せてもらったり、ニュアンスだけ伝えられて取り組んでみると、驚くほどスムーズに理解できる場合があります。私自身、実演で動きを目の前で見せてもらうことで、「あ、こういうことか!」と腑に落ちることが何度もありました。言葉で理屈を聞くよりも、動きそのものを見た方がイメージが掴みやすいのだと思います。言葉で細かく説明されるとピンと来なかった動作も、実演を見て「こんな感じかな」と感覚的に理解できると、一気に体が動くようになるものです。言葉を介さない分だけ、余計な先入観がなくなり、自分なりの解釈で動きを消化できるのだと思います。
思考の「余白」が深い理解を生む
すぐに言語化しないことで、思考に余白が生まれることも実感します。自分の中でモヤモヤするようなことや、理解しきれなかったことでも、言葉にできないまま一晩寝かせたり、他のことをしている時に、突然「ああ、そういうことか」「こういう風に感じてたんだな」と腑に落ちる経験はないでしょうか。言語化せず自分で考える余白を作ることで、深い思考を練られ、後から言語化するときにより質の高い洞察や表現ができます。逆に安易に言語化すると、本来の理解より浅い部分で止まってしまったり、実際の感覚とズレて理解してしまう恐れもあります。
意識的に言語化しようとする思考をいったん手放すことで、頭の中で情報が整理され、時間差で答えが見えてきます。私自身、行き詰まってモヤモヤするときは、敢えて言葉にせず放置してみるようにしています。そうすることで後になって点と点が繋がるように理解が深まることが多々あります。
オノマトペが引き出すイメージ
スポーツ指導では擬音語・擬態語などの、いわゆるオノマトペが効果を発揮する場面も多々あります。オノマトペ的な掛け声や表現は、一見ただの音に思えますが、その裏に具体的なイメージやリズムを伴っています。たとえば「グッ」「サッ」「バチーン」といった短い音で力の入れ具合やタイミングを表現すると、選手は言葉以上に鮮明なイメージを持ちやすくなります。結果として身体の反応も引き出されやすく、スキル習得やパフォーマンス向上につながるのです 。言葉数の少ないオノマトペだからこそ、余計な情報を削ぎ落として、本質的な動きを身体に刻み込めるのでしょう。
長嶋茂雄氏も指導の場面ではオノマトペ的な表現が多かったという話を聞いたことがあります。細かい動きの解説ではなく、あくまで感覚を伝える。そうすることで受け取った人たちが「なんとなくわかる」と感じ、プレーが改善していくこともあります。
詳細に言葉で定義しきらないからこそ、受け取り手のイメージが自由に膨らみ、結果的に本質的な理解や身体感覚の取得につながるのではないかと感じます。オノマトペは、言葉の持つ「伝える」という機能を超えて、「感覚を共有する」ツールとしてとても有効です。
抽象化力を鍛える
何でもかんでも言語化せずにしておくことは、物事を大きな枠組みで捉える訓練にもなります。言葉で細部まで定義づけてしまうと、その言葉の枠に思考が縛られてしまうことがありますが、言語化せずにいると全体像に意識を向けやすくなります。人間は「言語」で考えることに慣れていますが、ときには言葉を離れて物事を眺めることで、“森”を見る力が養われます。言語化しない時間を持つことで、頭の中でイメージや感覚を熟成させ、物事を抽象化する力を鍛える良い訓練になると思います。
終わりに
社会人になって、言語化することや言語化できる能力が重視されますが、私は言語化しない状態にも大きな価値があると考えます。言葉という型にはめずに物事に向き合うことで、自由な発想や深い理解が生まれます。
ビジネスでもスポーツでも日常生活でも、あえて言語化を手放す瞬間を持ってみる。そうすることで新たな気づきや成長を得られるかもしれません。
今回の内容が誰かの為になれば幸いです。ご拝読ありがとうございました。
最後に
映画を観た後に、すぐに解説を調べて気持ちを言語化したくなる癖は直したいです。